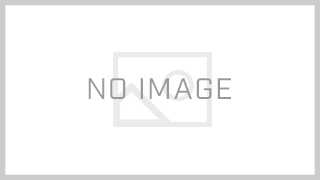市場で決まらない価格(必修解説)
需要と供給で決まらない価格
価格は需要と供給の関係で常に変動するわけですが、なかには、需要と供給では決まらない価格もあります。
1.独占価格
独占価格とは、1つまたは少数の企業が一方的に決める価格です。企業間の価格競争が弱まり、需要が少なくても価格は下がりにくく、価格が高い状態で固定化されやすくなります。競争相手がほとんどいないので、売り手は強気に「高くて嫌なら買うな」と言えるわけですね。消費者は、他に選択肢もないため、高くても買わざるをえません。つまり、独占価格は、消費者にとって不利になりやすいということです。
なお、独占とは1つまたは少数の企業が市場を支配している状態のことをいい、寡占とは少数の企業が市場を支配している状態のことをいいます。
消費者が不利益を受けることを防ぐために、独占禁止法という法律が制定されています。これは、市場での不公正な取引を防止し、健全な競争をうながすための法律です。公正取引委員会という機関が独占禁止法を運用し、不公正な取引がないか企業や市場を監視しています。
独占禁止法で禁止されている具体的な例として、カルテルがあります。カルテルとは、同業の企業が価格や生産量などについて協定を結び、競争を避けることです。企業がともだおれを避けて利益を確保するため、口裏を合わせて競争をしないということですね。これは消費者の不利益になるため、禁止されています。
2.公共料金
電気・ガス・水道料金、鉄道運賃・乗合バス運賃、郵便料金などは、国民生活に与える影響が大きいため、需要と供給に関係なく、国や地方公共団体が価格を管理しています。水道などのように、公企業が運営している場合も少なくありません。これらは価格が大きく変動することはありません。
必修公民にもどる